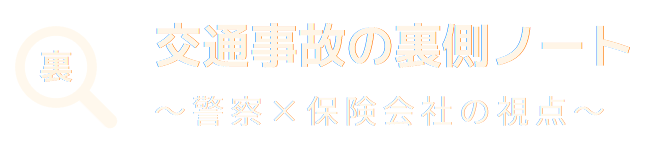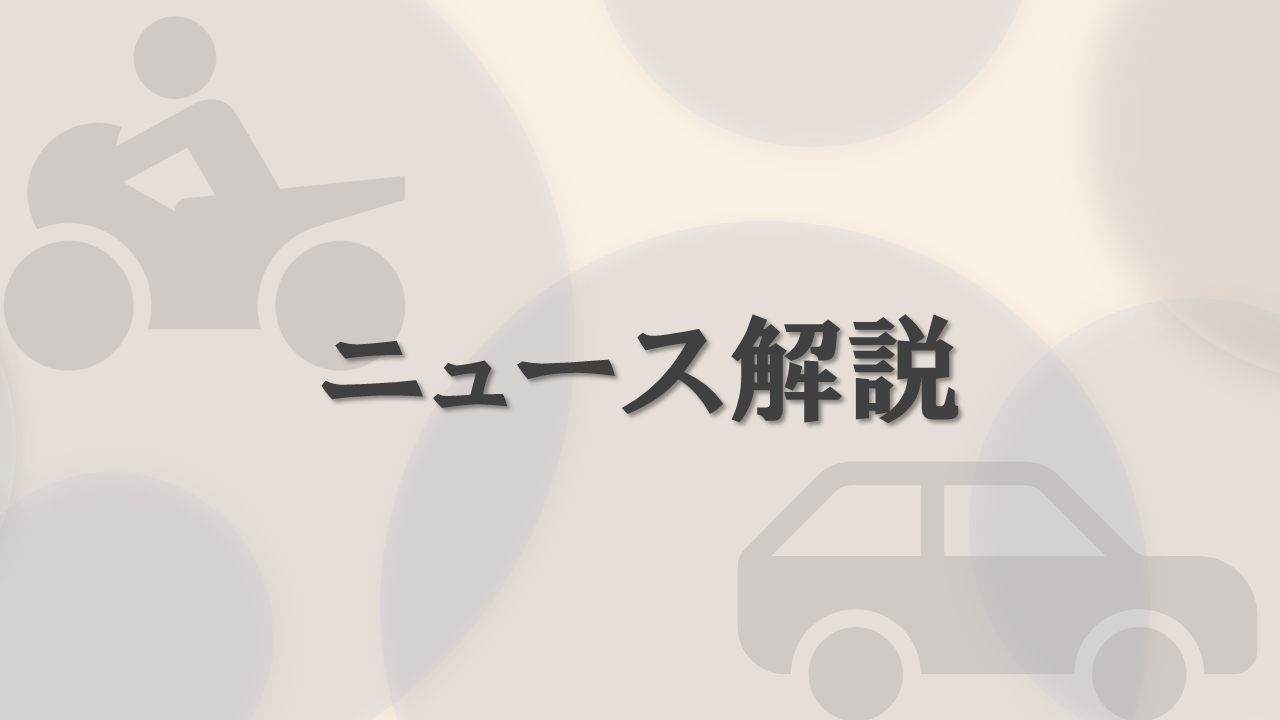【子供の自転車事故】親に数千万円の賠償命令!?わが子を加害者にしない、親の「監督責任」とは
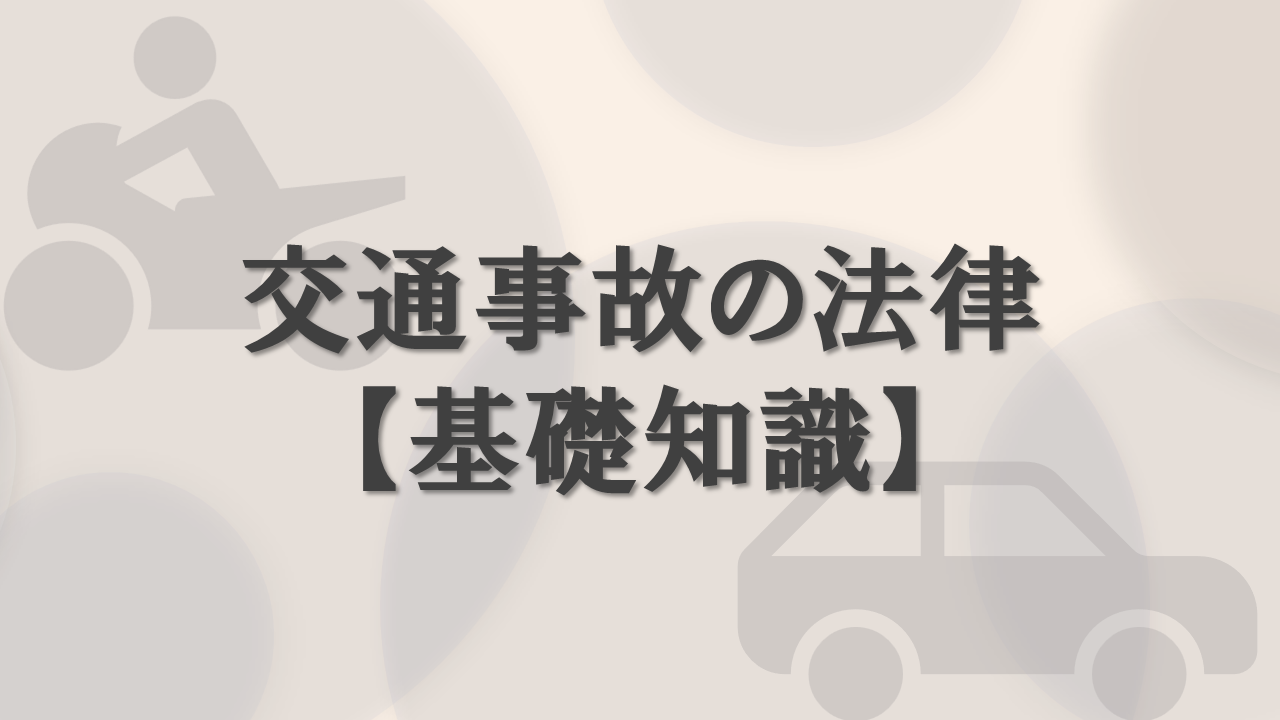
1. 「うちの子に限って…」その油断が、家族の未来を壊すかもしれない
ある日の夕方、あなたの小学生の子どもが、友達と自転車で遊んでいました。
その時、曲がり角でスピードを出し過ぎ、歩行者にぶつかって大怪我をさせてしまいました…。
あなたは思います。「子どもがやってしまったことだ。誠心誠意謝罪すれば…」
しかし、その事故の責任は、謝罪だけで終わるものではありません。
過去の裁判では、小学生の自転車事故で、その親に対し約9,500万円もの高額な賠償が命じられたケースも実在します。
「まさか、うちの子が…」
そう思うかもしれません。
しかし、子どもが起こした事故の責任は、監督者である親に重くのしかかってくるのです。
今回は、この「親の責任」について、法律がどう定めているのかを分かりやすく解説します。
2. 親の責任が問われる「3つのパターン」
子どもが事故の加害者になった時、親の責任が問われるパターンは、大きく分けて3つあります。
パターン①:子どもに「責任能力」がない場合(監督義務者責任)
法律では、自分の行動の結果を判断する能力(責任能力)がない子どもの行動の責任は、その監督者である親が負う、と定められています(民法714条)。
一般的に、11歳〜12歳くらいまでの子どもは、この「責任能力がない」と判断されることが多いです。この場合、親は「監督義務者」として、子どもの代わりに賠償責任を負います。
パターン②:親自身の「監督不行き届き」が問われる場合(親自身の不法行為責任)
子どもに責任能力がある年齢(中学生以上など)でも、親が安心できるわけではありません。
子どもの危険な行動を知りながら放置していたなど、親自身の「監督不行き届き」が事故の原因になったと判断されれば、親自身が不法行為責任(民法709条)を負うことになります。
【親の責任が『認められた』ケース】
16歳の息子が、何度も無免許運転を繰り返していることを知りながら、強く叱る程度で済ませていた両親。その後、息子が無免許運転で人身事故を起こしました。
裁判所は、「危険な行為を知りながら放置した」として、両親自身の監督義務違反を認め、賠償責任を負わせました。(大阪地判H15.9.22)
このように、子どもの危険なサインを見て見ぬふりをすることは、親として最も重い責任を問われる行為なのです。
パターン③:親が「車の所有者・管理者」である場合(運行供用者責任)
子どもが運転する車やバイクの事故では、親が「運行供用者」として、人身事故に対する賠償責任(自賠法3条)を負う可能性があります。
これは、たとえバイクが子ども自身のお金で買ったものであっても、
- 親と同居し、扶養されている
- バイクを通学などにも使っている
- バイクの保管場所が自宅である
といった状況があれば、「親も、そのバイクの運行を管理・監督すべき立場にあった」と見なされるのです。
「子どもが自分で買ったから関係ない」という言い訳は通用しません。親の監督下にある限り、その乗り物に対する責任からも逃れることはできないのです。
3. 「通常は危険でない行為」まで、親は監督すべきか?
では、親は子どものすべての行動を24時間監視しなければならないのでしょうか?
そんなことはありません。
最近の最高裁判所の判例では、興味深い判断が示されています。
小学生が、校庭でサッカーのフリーキックの練習中、ボールが道路に飛び出し、バイクが転倒した事故。
裁判所は、「校庭でのサッカーの練習は、通常は人に危険が及ぶとは考えられない行為であり、親がそれを具体的に予見することも困難だった」として、親の監督責任を否定しました。(最判H27.4.9)
この判例が示しているのは、親の監督責任にも限界がある、ということです。
しかし、翻って考えれば、自転車の運転のように、「通常、人に危険を及ぼす可能性がある行為」については、親が日頃から具体的な指導・監督をするのが当たり前、ということでもあります。
子どもを信じることは大切です。しかし、社会に対する責任を教え、危険から遠ざけることこそ、親が果たすべき最大の愛情なのかもしれません。