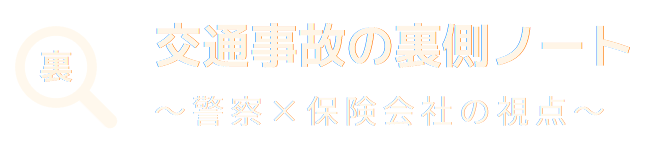【助手席の妻はOK?】事故の時、自賠責保険が使える人、使えない人『他人』の境界線とは
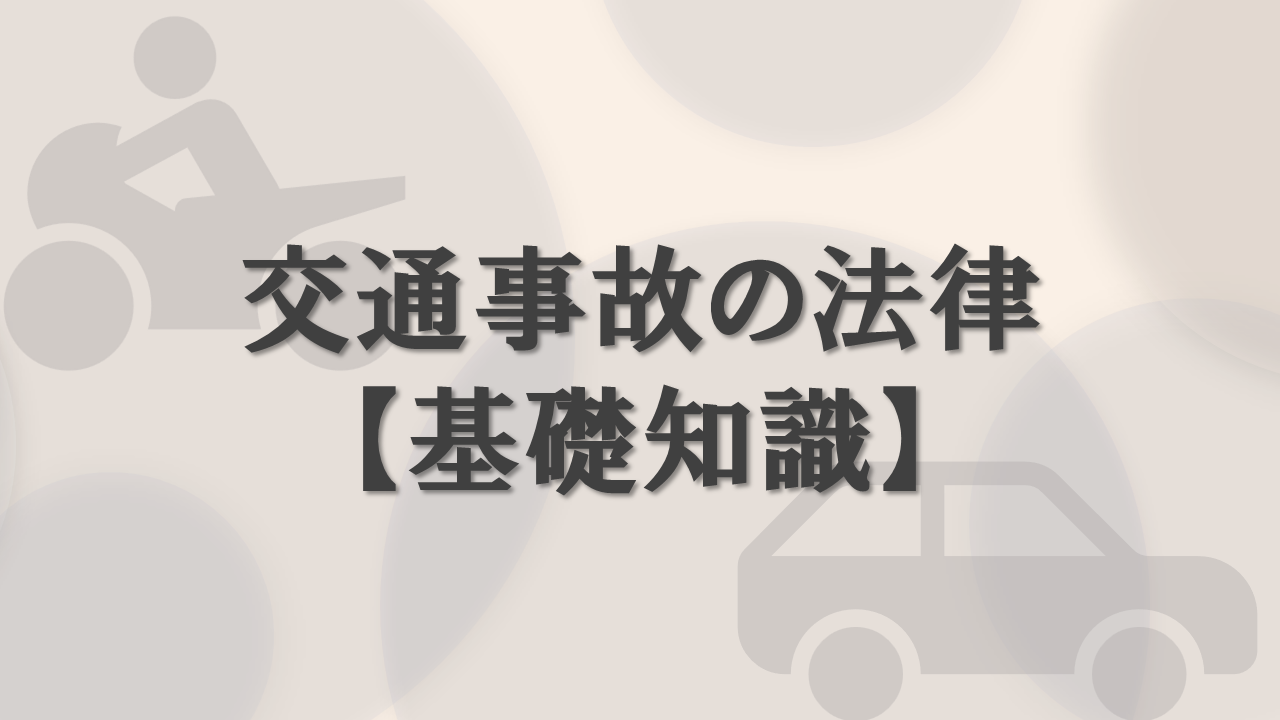
1. 夫が起こした事故。助手席の妻は「他人」ですか?
ある休日のドライブ。夫が運転する車の助手席に、妻であるあなたが乗っています。
夫の不注意でガードレールに衝突する自損事故を起こし、あなたはむち打ちになってしまいました。
さて、この場合、あなたは夫の自賠責保険を使って、治療費や慰謝料を受け取ることができるでしょうか?
答えは、「YES、できます」です。
「え、夫婦なのに『他人』なの?」と、不思議に思いますよね。
実は、自動車事故の損害賠償を定める法律(自賠法)でいう「他人」とは、私たちが日常で使う「他人」とは、少し意味が違うのです。
この「他人」に当てはまるかどうかは、あなたが万が一の事故の際に、自賠責保険という最低限の救済を受けられるかを決める、非常に重要な分かれ道になります。
2. 法律上の「他人」とは?たった2つの例外を除いた、すべての人
法律(自賠法)は、「他人」を非常にシンプルに定義しています。
「他人」とは、以下の2つの立場の人を『除いた』、それ以外の人全員のことです。
- 運行供用者(うんこうきょうようしゃ)
→ その車の運行をコントロールし、利益を得ている人。平たく言えば、車の持ち主や管理者のことです。(詳しくは前回の記事で解説) - 運転者
→ その車を運転していた人、またはバスガイドのように運転を補助していた人。
つまり、あなたがこの2つのどちらにも当てはまらなければ、たとえ運転手の妻であっても、親であっても、親友であっても、法律上は「他人」として扱われ、自賠責保険による救済の対象となるのです。
冒頭のケースで、妻が「他人」と認められたのも、
- 車は夫名義で、主に夫が使っていた(妻は運行供用者ではない)
- 妻は免許を持っておらず、運転していなかった(妻は運転者ではない)
という理由からでした。
3. あなたは「他人」じゃないかも?保険が使えない3つのケース
逆に、あなたが「他人」として扱われず、自賠責保険の対象外となってしまうのは、どんなケースでしょうか。具体例を見ていきましょう。
ケース①:自分の車を、友人に運転させていた場合
あなたが所有する車で、友人に「運転お願い!」と頼んで、自分は助手席に乗っていたとします。
この時、事故が起きてあなたが怪我をしても、あなたは「他人」にはなれません。
なぜなら、あなたは車の所有者として「運行供用者」にあたるからです。自分で自分を救済することはできない、という理屈です。
ケース②:会社の車を、仕事で運転していた場合
あなたが会社の営業車を運転中に事故を起こし、怪我をした場合。
この時、あなたは会社(運行供用者)のために運転する「運転者」にあたるため、「他人」にはなれません。
(※この場合は、自賠責保険ではなく、労災保険の対象となります)
ケース③:ラリーのナビゲーターとして同乗していた場合
ラリー競技で、運転手の横で地図を読んだり、指示を出したりするナビゲーターとして同乗していた場合。
あなたは、運転を直接補助する「運転補助者」と見なされるため、「他人」にはなれません。
このように、「その車の運行に、どれだけ責任を負う立場だったか」が、「他人」であるかどうかを判断する重要な基準になります。
4. 「運転手」から「他人」に変わる瞬間
では、トラックの長距離ドライバーが、相棒と交代して助手席や仮眠室で休んでいる時に事故が起きたら、どうなるでしょう?
この場合、休んでいたドライバーは、その瞬間は運転業務から離脱していると見なされ、「運転者」から「他人」の立場に変わります。
そのため、自賠責保険による救済の対象となるのです。
ポイントは、「事故が起きた、まさにその瞬間、あなたはどんな立場で車に関わっていましたか?」ということです。