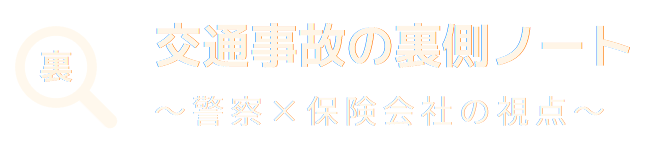【会社の車で事故】従業員の無断運転でも、なぜ会社が責任を負うのか?経営者が知るべき全知識
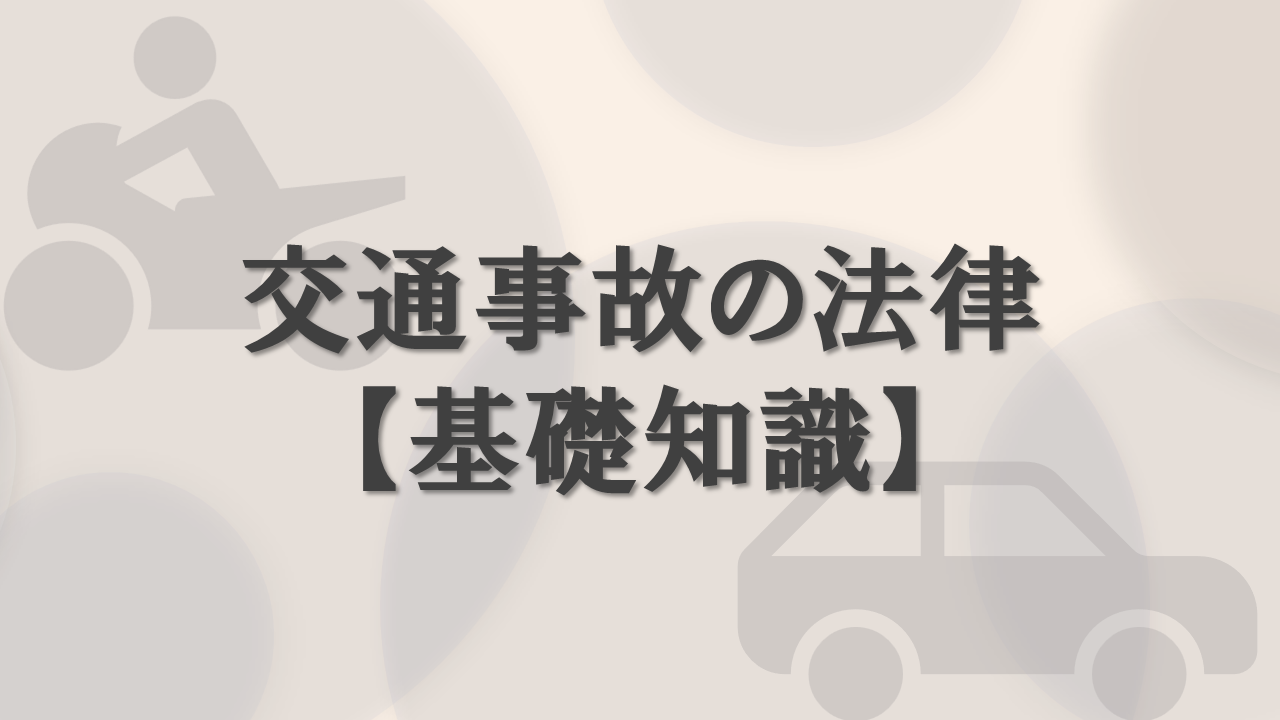
1. 「あいつが勝手に…」その言い訳、通用しません!
ある日の休日、あなたの会社の従業員A君が、会社に置いてあった営業車を無断で持ち出し、プライベートのドライブ中に人身事故を起こしてしまいました。
A君は言います。「会社の車を勝手に使ってしまい、本当に申し訳ありません…」
あなたは思います。「就業時間外に、無断で、しかも私用で使ったんだ。会社の業務とは一切関係ない。会社の責任はゼロのはずだ…」
しかし、その考えは非常に危険です。
たとえ従業員の完全な無断使用であっても、会社の車の管理体制に不備があったと判断されれば、会社も被害者に対して数千万円もの損害賠償責任を負う可能性があるのです。
今回は、この「従業員が起こした事故の会社の責任」について、経営者や管理者の方が絶対に知っておくべき、厳しい現実を解説していきます。
2. なぜ会社は、従業員の「プライベートの事故」にまで責任を負うのか?
会社が従業員の事故で責任を問われる法的根拠は、主に2つあります。
- 使用者責任(民法715条)
→ 「事業の執行について」従業員が起こした事故の責任は、使用者である会社も負いなさい、というルール。業務中の事故なら、当然この責任が問われます。(※これは人身・物損を問いません) - 運行供用者責任(自賠法3条:人身事故の被害者に対する賠償責任)
→ これが今回のキモです。前々回の記事で解説した通り、「車の所有者・管理者」として、非常に重い責任を負います。そしてこの責任は、たとえ業務時間外の無断運転であっても、簡単には免れることができません。
裁判所は、「たとえ従業員が無断で私的に使っていたとしても、客観的・外形的に見て、会社の管理下にある車が起こした事故である以上、所有者である会社にも責任がある」と考える傾向にあるのです。
3. 会社の責任を分ける「車の管理体制」
では、どんな場合に会社の責任が問われてしまうのでしょうか?
裁判所が重視するのは、「会社として、無断運転を防ぐための努力を本当に尽くしていたか?」という点です。
【会社の責任が『認められた』ケース】
従業員が、会社のスペアキーを使って社用車を無断で持ち出し、事故を起こしました。会社は「私用運転は禁止していた」と主張しましたが、裁判所は「日常的にスペアキーを従業員に渡していた会社の管理体制は甘い」として、会社の責任を認めました。(大阪地判H18.7.26)
このように、「ルール上は禁止」していても、カギの管理がずさんで、従業員がいつでも車を持ち出せるような状況だった場合、会社の責任は免れられないのです。
会社の責任を免れるためには、「無断運転だった」という主張だけでは不十分です。
「就業後のカギは、管理者が金庫で厳重に保管していた」「運転日報で、車の使用状況を毎日チェックしていた」といった、無断使用を許さないための、具体的な措置を講じていたことまで証明する必要があるのです。
4. 「マイカー通勤」の事故も、他人事ではない
さらに注意が必要なのが、従業員の「マイカー」による事故です。ここでも、会社の「関与の度合い」が厳しく問われます。
【会社の責任が『認められた』ケース】
会社は、従業員がマイカーで工事現場から寮に帰ることを事実上黙認していました。寮の駐車場も使わせており、会社はそのマイカー利用から事実上の利益を得ていたと言えます。その従業員が、帰宅途中に事故を起こしました。
裁判所は、「会社は、その車の運行を間接的に指揮監督できる立場にあった」として、会社の責任を認めました。(最判H1.6.6)
【会社の責任が『否定された』ケース】
会社にはマイカー通勤の規則がありましたが、その従業員は正規の申請や許可を得ていませんでした。あくまで自己の便宜のためにマイカー通勤を選択しており、会社が積極的に業務に利用していたわけでもありませんでした。その従業員が、帰宅途中に事故を起こしました。
裁判所は、「会社が運行から利益を得ていたとも、運行を支配していたとも言えない」として、会社の責任を否定しました。(東京地判H25.3.14)
この2つの例の分かれ目は、「会社が、従業員のマイカー利用をどこまで把握し、容認し、そこから利益を得ていたか」という点です。たとえ従業員個人の車であっても、会社がその利用を黙認し、業務に組み込んでいると見なされれば、もはや「従業員個人の問題」では済まされません。